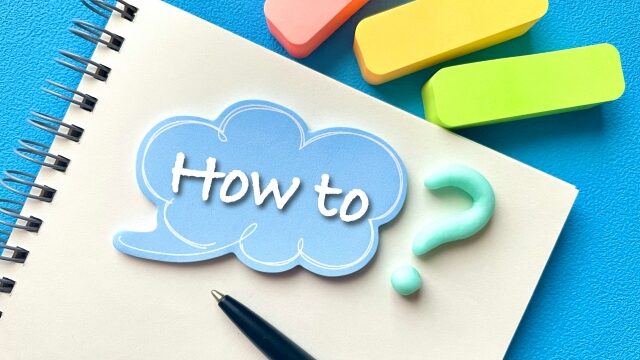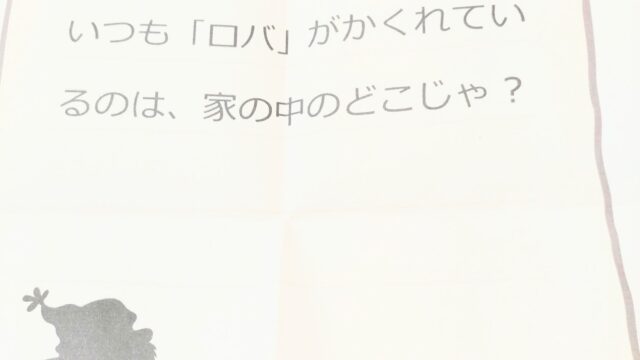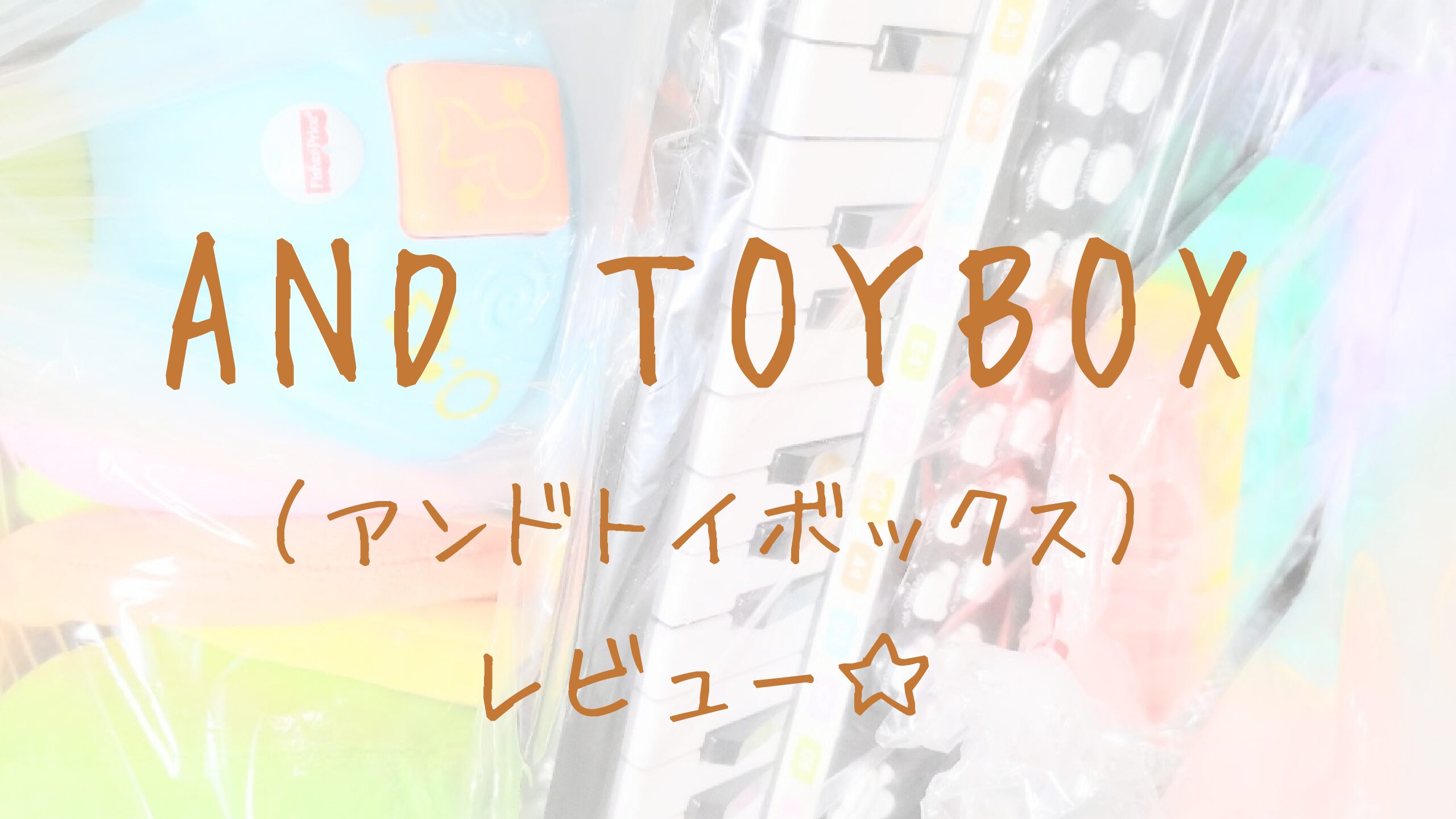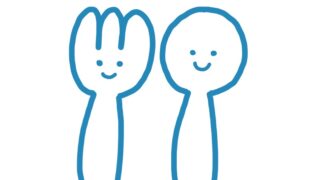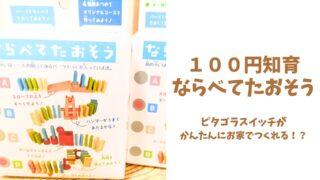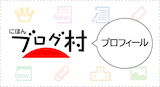【オススメ教育本】小学生のなやみを解決!『親子で知りたい小学校最強ライフハック70』

今回はオススメの教育本についてのお話です。
皆さんは今の子どもたちが置かれている状況や未来が自分たちの頃とは大きく違っていることを意識したことがありますか?
日経トレンディの『2030年大予測』(2023年1月号)の中で、2022年に12歳以下の子供たちをα世代と呼び、6つの特徴が挙げられています。
- 何かに興味を持っても長続きしない
- 分からないことは調べず、次の興味関心に移りやすい
- 楽しいだけではすぐに飽きる
- 「答えありき」で考える
- 探せば答えが見つかるものごとが多く、自分が動くための理由を考えがち
- 価値観が多様化し、コミュニティーが細かく分かれがち
今子どもたちに当てはまっていることも多く、この記事を読んで私ははっとしました。
今の子どもたちは私たちの頃と大きく変わっているのだと。
それは学校教育や学校内でのトラブル、学習方法に関しても言えることです。
でも、私も含めどんな風に変わって、何をしたらいいのか具体的には分からず不安と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこでオススメしたいのがこちらの本です!
『親子で知りたい 小学校最強ライフハック70』 坂本良晶
- 子どもたちの通う学校がどう変わったのか
- 家庭学習をどのように進めていけばいいのか
- 学校でのトラブルとどう付き合っていけばいいのか
といった不安への答えが知りたい方へ☆
令和の小学校はどう変わったのか・私たちは何をすべきなのかをぜひ一緒に考えてみましょう!

親子で一緒に考えたいお話がいっぱいです!
著者坂本先生について
まず、著者の坂本良晶先生についてのご紹介から☆
坂本先生は東証一部上場企業の寿司チェーン店で、店長として全国店舗売上1位にもなった 社会人としてのキャリアをお持ちです。
社会人経験後、教員免許取得・採用試験を経て小学校の教員として現在もご活躍されています。
また、マイクロソフト認定教育イノベーターとして、タブレットを使った教育実践などでも有名です。
父親としての視点もお持ちで、学校現場だけでなく、Twitterや様々なメディアなどで日本教育の現状や今後について発信しておられます。
>> 坂本良晶 小学校教員のための教育情報メディア「みんなの教育技術」by小学館
そんな坂本先生が、子どもたちがスムーズに学校生活を送れるように知っておいてほしいこと・やってほしいことを分かりやすくまとめてくれているのがこちらの本です!
『親子で知りたい小学校最強ライフハック70』のオススメポイント☆

次に本書のオススメポイントについて紹介したいと思います。
本書は6つの項目に分かれています。
タブレット学習の導入で学習がどのように変わったのか

まず第1章(1時間目)についてです。
第1章では『GIGAスクール構想』のメリットやデメリットなどを中心に令和の小学校の変化が分かりやすくまとめられています。
私たちの頃にはなかったタブレット端末。
でもタブレットは今や、子どもたちにとって”あって当然の文具”となっています。
タブレット導入のメリットとして
- 1人1人の得意・不得意・興味関心に合わせて自発的に学べる
- みんなで協力しながら難しい問題をクリアできたり、様々なアイデアを生み出せる
- 距離を越えて色んな土地の子どもたちと交流できる
などが挙げられています。
反対にAI学習のデメリットとして、弱みを自分自身で分析する(メタ認知力)機会を奪われてしまう点にも触れられています。

また、子どもたちにとって必要な『21世紀スキル』についても触れられています。
今子どもたちに求められるスキルは私たちの頃とは変わっているんです!
ぜひ、どのように小学校が変わっているのかやどのようなスキルが求められているのかに注目して読んでみてください。
その他
- 小学校における発達障害の対応について
- 普通の学校以外の学校(オルタナティブスクール)
などについても書かれているので、ご参考にしてみてくださいね☆
教科ごとの学習ポイント

第2章(2時間目)では家庭での学習のコツなどについてです。
教科ごと(国語・算数・理科・社会・体育・図工・英語・総合)にそれぞれの学習の意味や学習ポイントなども具体的に書かれています。
例えば国語に関して、
- 愛情を持って、できるだけていねいな正しい言葉で子どもと接する
- 月に1回は本を買う&図書館へ行く
- お風呂にひらがな表や漢字表を貼っておく
- パソコンによるタイピングゲームでローマ字を練習する
など、そのまま家庭で実践できることもたくさんあります。
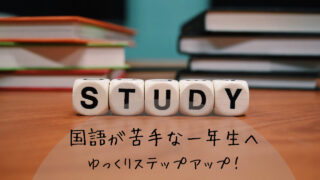
また、学習の変化で一番印象的だったのは体育です。
私たちの頃の体育は「できない」技(逆上がり)を練習で「できる」に変えていくものでしたよね?
でもこれからの体育は
- 「できる」範囲の運動を楽しむ
- 全員が楽しめるためのルールをつくる
ことで、生涯にわたって身体を動かすことを楽しむ教育に変わろうとしています。
ぜひ、子どもたちが学ぶ教科それぞれについて、しっかり理解して家庭でも実践していきたいですね☆
令和的・小学生のトラブルとは?

第3章(3時間目)では、『令和的・小学生のトラブルとの付き合い方』です。
- お金やスマホ・ゲームに関するトラブル
- ブラック校則
- テストの採点
- 忘れ物に関するトラブルの対処法
など、学校内外の子どもたちにまつわる様々なトラブルについて書かれています。
子どもたちのトラブルも私たちの頃と令和ではこんなにも違うんだと驚かされます!
例えば、お金に関してのトラブル。
私たちの頃は”おごるおごらない”や”借りる借りた”など実際に持っているお金がトラブルの元でした。
令和のお金トラブルは『課金』です。
スマホゲームなどにより、子どもたちは手元に持っている以上のお金をネット上で簡単に使うことができます。
本書では
日ごろからお金の尊さを伝えること
お金を稼ぐのがどれだけ大変かお金の量感を肌感覚で理解させることが重要(お小遣い制など)
とあります。
また、持ち物のトラブルに関しての項目では
先生として「文房具として『質のよいもの』を持たせてほしい」とお願いされていました。
筆箱の中を最高の状態に保つことで、環境を整えて子どものサポートをする
ことが大切とのこと!
こちらを読んでから、私も子どもの筆箱は毎日チェックするようになりました。
我が家の男子は消しゴムをすぐちぎって遊ぶし、鉛筆がどれだけ短くなっても使い続けています。
男の子の親御さんは今すぐ筆箱の中身をチェックしてみましょう!
『筆箱の充実度』と『子どもの学力』には相関関係があるようですよ!
「〇〇育」はこんなにも変わっている!

第4章では小学校での「〇〇育」最新事情について触れられています。
- 全部食べる時代は終わった食育事情
- LGBT教育
- 金融教育
- 人権教育
など、知らなかったでは済まされない令和の〇〇育事情は、ぜひ親御さんだけでなくお子さんも一緒に読んでほしいものばかりです。
また
- これから重要視される「話す力」について
- 「振り返り」「探求学習」を重要視する教育のトレンド
など、子どもたちの学習において何が大切にされているのかを知っておくことは大切かなと思います。
- 一緒にニュースを見たり新聞を読む
- 学習の後に「どうだった?」「次はどうする?」と、振り返る
など私たちができることも挙げられています。

できることからはじめたいですね☆
人生を豊かにする「ライフワーク」を子どもたちへ☆
第5章(5時間目)は『令和の小学生に伝えたい「職業観』についてです。
子どもたちの就く職業は、私たちの職業とは違ったものになるようです。
また、仕事がパラレルキャリア(複数のビジネス・複数の収入源など)化し、複数の仕事を持つことが当たり前になると本書では書かれています。
この章を読めば、そのためにどんな力が必要とされるのかや親として何を大切にすべきかがよく分かります。
私たちが考えているより、子どもたちの未来ってずっと広がっているんですよね☆
私も今の当たり前に固執せず、子どもの好きを大切にしたいと思いました。
子どもと一緒に
ミッション = 自分がこの世界で何を成し遂げたいか
を考えてみましょう!
通知表のお話☆
最後は課外授業として「通知表」のお話が書かれています。
意外と知らないことだらけの通知表ですが、皆さんはどうでしょうか?
こちらの章では、通知表の付け方などがかなり詳しく書かれています。
これほどはっきり書かれている本は他にはないと思いますよ!
昔と比べて主体的に学習できているかが評価として大きくなっているようです。
先ほどの職業観にも通じますが、こちらの章でも好きなことを伸ばすことの大切さが書かれています。
「苦手を克服してバランスよく」するよりも、「突出した5をつくる」アプローチのほうが大切だと考えています。そうやってとがらせた長所は、未来を切り開く頼りがいのある武器になってくれるはずです。
『親子で知りたい小学校最強ライフハック70 課外授業 気になる通知表のはなし』

子どもの好きを伸ばしていきたいですね☆
最後に
実はこちらの本をオススメしたかったのは、坂本先生の最後のあとがきにとても共感したからなんです☆
本書は最後に
お風呂で一緒に覚えたひらがな。もう寝たいのに何度も読んでとせがまれた絵本。急な発熱で駆け込んだ救急病院。そんな一瞬一瞬の積み重ねが、わが子との大切な思い出であり、幸せなのです。
(中略)
子どもとの「今」の時間を少しでも多く過ごすための虎の巻のように使っていただけたら、とてもうれしく思います。
『親子で知りたい小学校最強ライフハック70 おわりに』
と書かれています。
私たちがむやみやたらに子どもたちの将来を不安に思ってるだけでは何も変わらないんですよね。
子どもたちの将来や今がどう変わったのかを知ることで、「今」できることを積み重ね、「今」の子どもたちとしっかり向き合う
ことが大切なんだと改めて気づかされました。

子どもたちとの「今」の時間を大切にしましょう☆
にほんブログ村